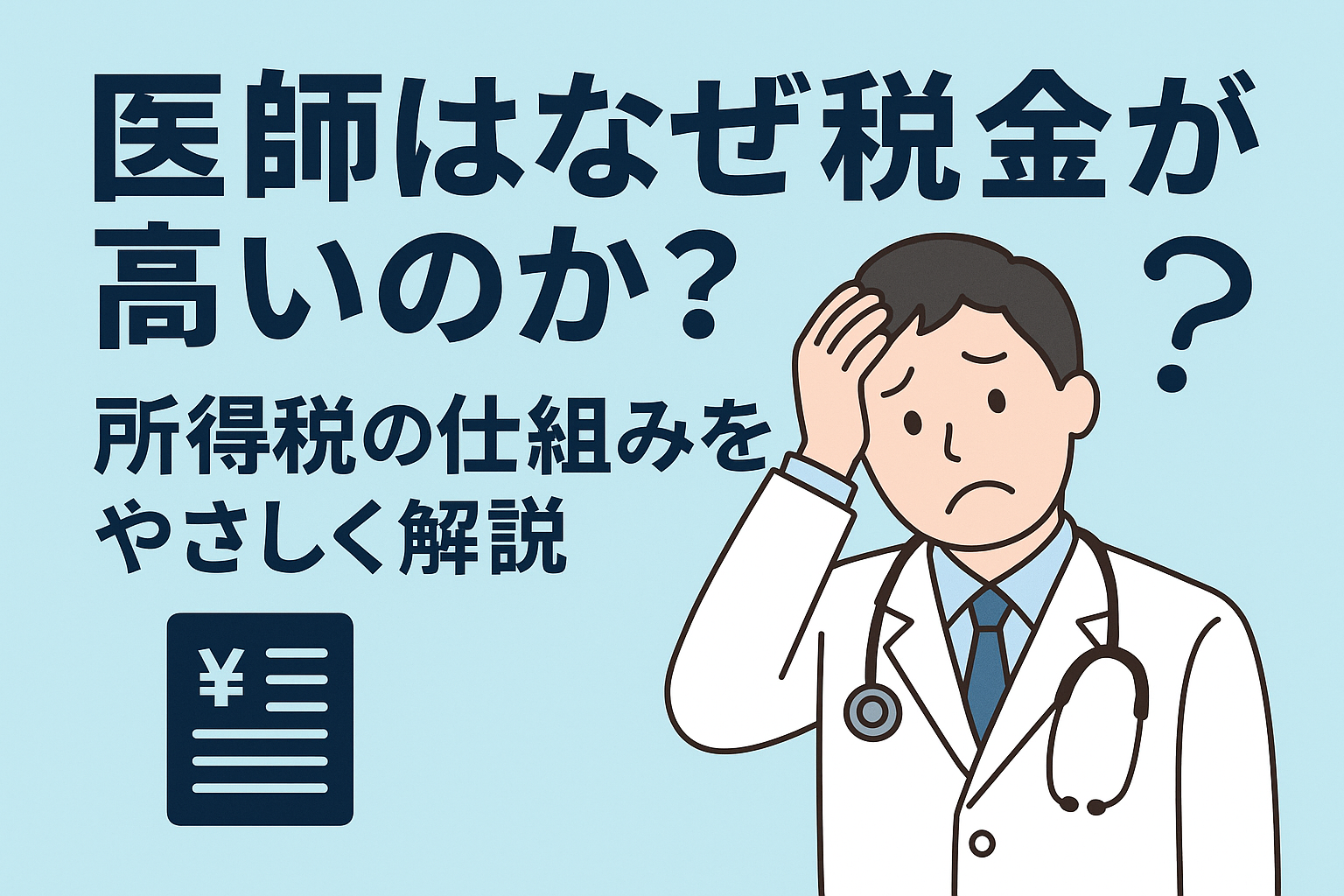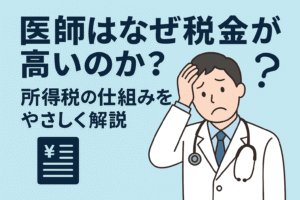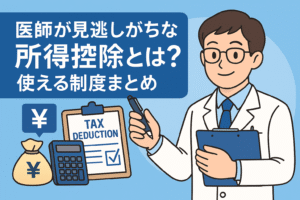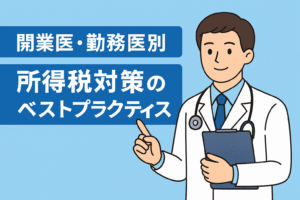医師が抱える税金の悩み|所得税の仕組みを理解して節税に役立てよう
医師の皆さん、税金について「高すぎる」と感じたことはありませんか?
勤務医も開業医も、収入が高い分だけ税金の負担が大きくなるのは避けられない現実です。
「なぜこれほど税金を支払うのか」「少しでも節税できないのか」と疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
その解決の第一歩は、税金の仕組みを正しく理解することです。
知識があることで節税方法を見つけやすくなり、将来の財務戦略にも役立ちます。
この記事では、医師の方向けに所得税の基本的な仕組みをわかりやすく解説していきます。
所得税は「収入」ではなく「所得」にかかる
まず理解しておきたいのは、所得税は「収入」そのものに課されるものではないという点です。
収入から必要経費や控除を差し引いた「所得」に対して税金が課せられます。
たとえば、開業医の場合は診療報酬から医療機器、人件費、家賃などの経費を差し引いた金額が所得になります。
勤務医の場合は経費を直接差し引くことはできませんが、給与所得控除という制度により収入の一部を経費とみなして差し引くことが可能です。
このように、勤務医と開業医では所得の計算方法が異なりますが、どちらも所得に対して税金がかかるという点は共通しています。
医師の立場によって異なる所得の種類と課税対象
所得税法では、所得を10種類に分類しています。
医師の方に関係が深いものを挙げると、以下のようになります。
- 給与所得:勤務医の給料・賞与
- 事業所得:開業医の診療報酬から経費を差し引いたもの
- 配当所得・譲渡所得・不動産所得など:資産運用や投資によって得られる所得
勤務医は主に給与所得、開業医は事業所得が中心ですが、資産運用や副業を行っている場合は他の所得区分も関わってくるため注意が必要です。
また、医療法人を設立している場合、法人から支払われる役員報酬は給与所得として扱われる点も理解しておきましょう。
法人と個人は税務上別人格となるため、医療法人の利益には法人税がかかります。
所得税の計算ステップを理解する
所得税の計算は、以下のステップで進められます。
- 収入を所得区分に分類する
- 必要経費や給与所得控除を差し引く
- 所得控除(基礎控除・扶養控除・社会保険料控除など)を適用する
- 課税所得に税率をかけ、所得税額を計算する
- 税額控除や源泉徴収額・予定納税額を差し引く
- 最終的な納税額または還付額を確定する
これらを順に行うことで、最終的な所得税額が決まります。
所得税の税率
所得税の税率は、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。(分離課税を除く)
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」
この表に従い、課税所得金額に応じた税率をかけて税額を算出します。
具体例:課税所得が700万円の場合
課税所得が700万円の場合、所得税率は23%で、控除額は63万6千円です。
計算式は次のとおりです。
700万円 × 23% − 63万6千円 = 97万4千円
これが所得税額となります。
さらに復興特別所得税(所得税の2.1%)が加算され、最終的な納税額が決まります。
税額控除や源泉徴収を活用して税額を調整する
計算された所得税額から、住宅ローン控除などの税額控除を差し引くことができます。
また、勤務医の場合は源泉徴収で既に納めている税額も反映され、過不足が調整されます。
開業医の場合、前年の税額によっては予定納税が必要になる場合があり、その分も確定申告時に調整されます。
納付額が不足していれば追加納付、納めすぎていれば還付という形になります。
医師が所得税を理解するメリット
所得税の仕組みを理解することで、次のようなメリットがあります。
- 節税ポイントを把握し、適切に経費や控除を活用できる
- 医療法人化や投資などを踏まえた財務戦略を考えやすくなる
- 将来のライフプランを立てる上での基礎知識となる
特に医師は本業が忙しいため、税務知識が不足しがちですが、知っているかどうかで大きな差が生まれます。
まとめ|税務に不安がある場合は専門家への相談も選択肢
所得税の計算は決して単純ではありません。
制度を理解し、適切に対応することで節税効果を高め、将来の資産形成にも役立てることができます。
ただし、個別の状況によって最適な方法は異なるため、専門家のサポートを受けることも大切です。
税金に関する悩みや不安がある場合は、税理士ドットコムなどの専門家検索サービスを利用して、ご自身に合った税理士を探すのも一つの方法です。
また、筆者が在籍する会計事務所でも、医師の皆さまが抱える税務や財務に関する疑問や不安について、わかりやすく丁寧にサポートしています。
税金のことをもっと知りたい、具体的なアドバイスが欲しいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
次回予告|医師のための所得控除を徹底解説
次回は、「医師が見逃しがちな所得控除とは?使える制度まとめ」をお届けします。
控除を上手に活用することで、さらに税負担を抑える方法をわかりやすく解説します。
ぜひご期待ください。