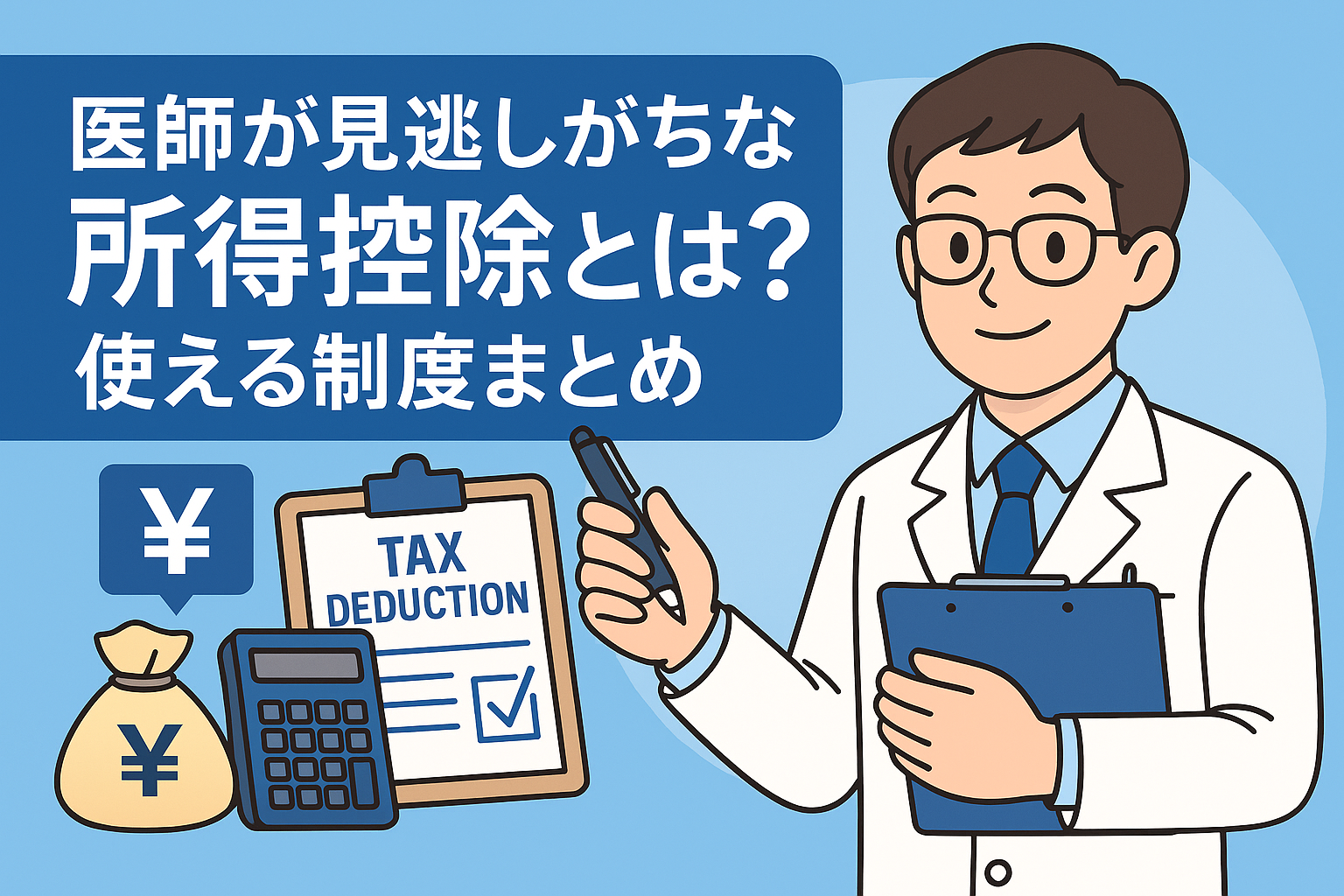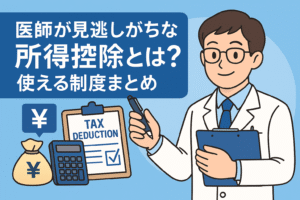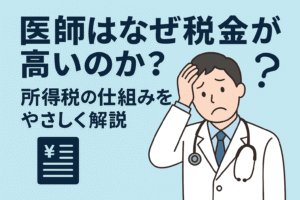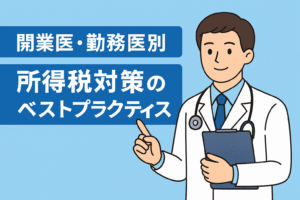はじめに|医師が見逃しやすい所得控除を正しく理解しよう
医師の皆さん、所得税の計算で重要な役割を果たす「所得控除」を十分に活用できていますか?
高所得になりがちな医師の方々は、税金の負担も大きくなりやすいため、所得控除を適切に活用することで課税所得を抑え、所得税を軽減することが非常に重要です。
しかし、日々の忙しさの中で、意外と使える控除を見逃してしまっているケースも少なくありません。
この記事では、医師の皆さまが押さえておきたい代表的な所得控除について、わかりやすくまとめます。
勤務医・開業医それぞれの視点から、活用のポイントも解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
所得控除とは|税金を減らすための大事な仕組み
所得控除とは、所得税を計算する際に、課税対象となる所得から差し引くことができる制度です。
控除を適用することで課税所得が減り、結果として所得税額そのものが少なくなります。
所得控除には、誰でも受けられるものと、一定の条件を満たすことで適用されるものがあります。
正しく理解し、もれなく活用することが、税負担の軽減につながります。
医師が活用できる主な所得控除一覧
基礎控除(全員が対象)
すべての納税者が受けられる控除で、基本は48万円が差し引かれます。
ただし、所得が2,400万円を超えると控除額が減額され、2,500万円超で適用不可となる点に注意が必要です。
配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の収入が一定以下である場合に適用できます。
特に配偶者がパート勤務などの場合、条件を満たす可能性があるため、忘れずに確認しましょう。
扶養控除
子どもや親など扶養している家族がいる場合に適用できます。
特に大学生の子どもや同居している親の扶養などは、該当しやすいポイントです。
社会保険料控除
健康保険、厚生年金、国民年金などの保険料は全額が所得控除の対象になります。
勤務医の場合は、給与から差し引かれている健康保険料と厚生年金保険料が対象です。
開業医の場合は国民健康保険料や国民年金保険料、医療法人役員の場合は給与から差し引かれる厚生年金・健康保険料(協会けんぽや医師国保など)が対象となります。
それぞれの立場によって支払う保険料の種類は異なりますが、いずれも全額が社会保険料控除として所得から差し引くことができます。
生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険や地震保険に加入している場合、一定額が控除対象です。
医療従事者は万一に備えて加入していることが多いため、該当する方も多いでしょう。
医療費控除
年間の医療費が一定額(10万円または総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に利用できます。
自費診療や家族の医療費がかさんだ場合は忘れずに申告しましょう。
小規模企業共済等掛金控除
開業医や医療法人の役員で加入している場合、掛金全額が所得控除となります。
将来の退職金準備にもなり、節税と資産形成の両面で有効です。
見逃しがちなポイント|勤務医と開業医・医療法人役員の場合
勤務医の場合
- 給与所得控除だけでなく、医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)なども活用することで節税が可能です。
- 共働き世帯の場合、配偶者控除や扶養控除の適用可否は必ず確認しましょう。
開業医・医療法人役員の場合
- 小規模企業共済やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、事業者向けの節税制度を積極的に活用しましょう。
- 医療法人化している場合、法人で加入する保険と個人で加入する保険のいずれも必要になるケースがあります。
保険の種類や税務上の取扱い(経費計上の可否や所得控除の対象になるかなど)は法人・個人で異なるため、それぞれの目的やメリットを踏まえて適切に管理することが重要です。 - また、医療法人から役員報酬を受け取る場合、社会保険は協会けんぽ+厚生年金または医師国保+厚生年金という組み合わせになるケースがあります。
いずれの場合も社会保険料控除として税務上の影響があるため、正確に把握しておく必要があります。
まとめ|所得控除を賢く活用し、税負担の軽減を目指そう
所得控除は、医師にとって非常に重要な節税ポイントです。
高所得になるほど、適用できる控除を漏れなく活用することで、年間の税負担を大きく抑える効果があります。
多忙な日々の中では、こうした細かな制度を見逃しがちですが、今一度確認し、適切に活用していきましょう。
また、制度は年々変更されるため、最新の情報をもとにした対策が不可欠です。
必要に応じて専門家に相談し、自分に合った方法を検討するのが賢明です。
税金に関する悩みや不安がある場合は、税理士ドットコムなどの専門家検索サービスを利用して税理士を探すのも良いでしょう。
また、筆者が在籍する会計事務所でも、医師の皆さまの税務・財務について丁寧にサポートしております。
ぜひお気軽にご相談ください。
次回予告|医師の経費と事業所得の考え方
次回は、「医師の経費と事業所得の考え方」をお届けします。
勤務医・開業医それぞれのポイントについても詳しくご紹介する予定ですので、ぜひご期待ください。