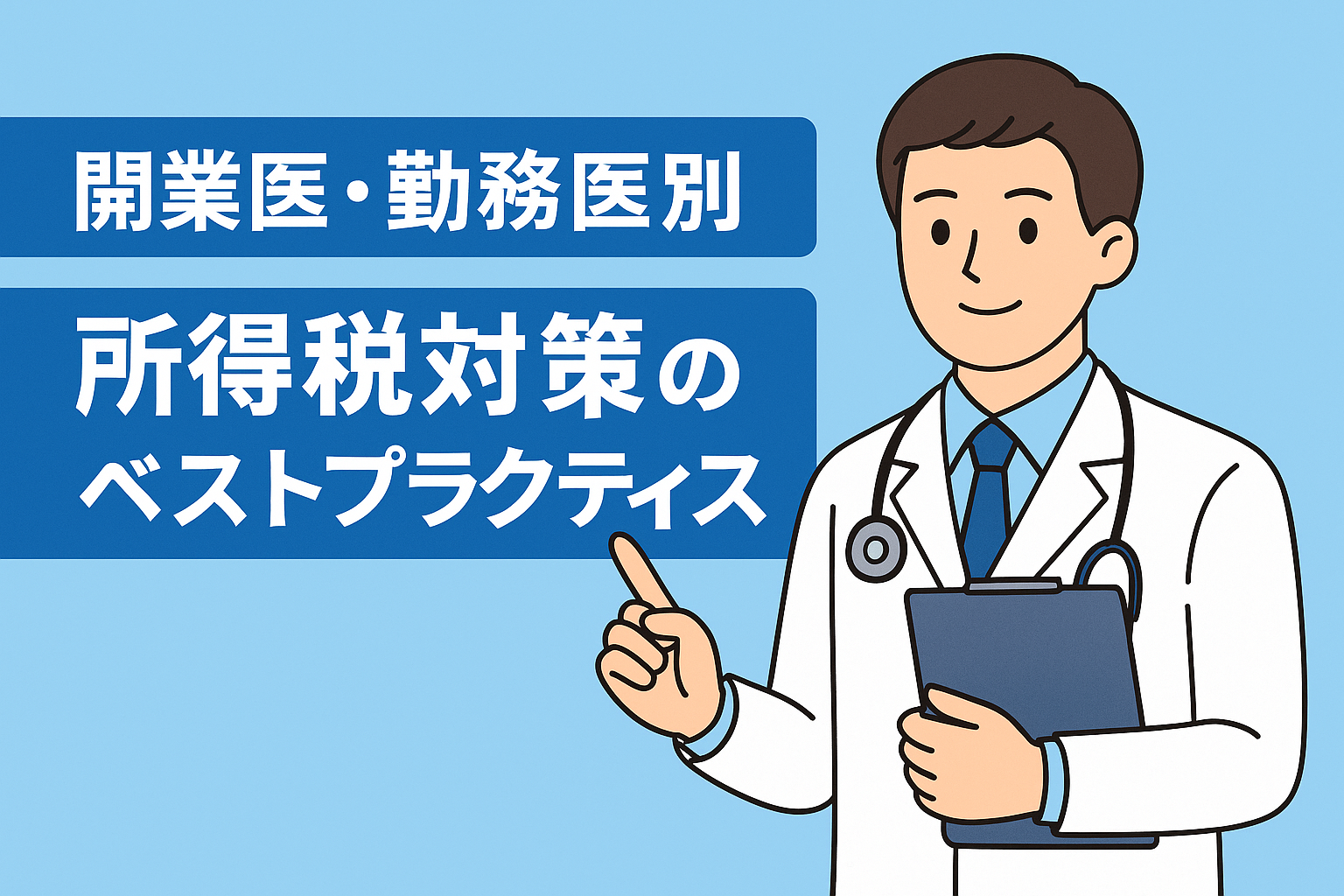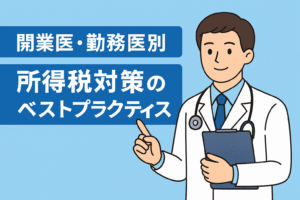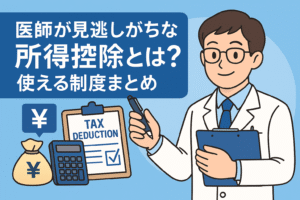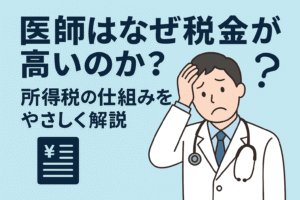はじめに|医師が取り組むべき所得税対策とは?
これまでの記事で、医師の皆さんに向けて所得税の仕組みや控除、経費の考え方などを解説してきました。
今回はその集大成として、勤務医と開業医、それぞれの立場に応じた所得税対策のベストプラクティスをご紹介します。
正しい知識と適切な対策を行うことで、税負担を抑え、より安定した財務基盤を築くことが可能になります。
ぜひ、自身の状況に合わせた対策を考えるきっかけにしてください。
所得税対策の基本方針
所得税対策は、次の2つのアプローチで考えることが重要です。
- 課税所得を減らす(控除や経費の活用)
- 税額控除や優遇制度を活用する
この基本を押さえた上で、勤務医と開業医それぞれの具体的な対策を見ていきましょう。
勤務医が実践すべき所得税対策
勤務医は給与所得が中心となるため、経費の自由度は低いものの、活用できる制度は多くあります。
所得控除をもれなく適用する
- 基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの基本的な控除
- 社会保険料控除(給与から天引きされる健康保険・厚生年金など)
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 医療費控除(年間医療費が一定額を超えた場合)
- ふるさと納税(寄附金控除)は特に手軽で効果的
副業・スポットバイト収入は適切に経費計上する
- 医師バイトなど業務委託収入がある場合は、必要経費を差し引くことで課税所得を減らせる
iDeCo・NISAの活用
- iDeCo(個人型確定拠出年金)は掛金が全額所得控除になる
- NISAは非課税で資産形成が可能
勤務医でも、控除と資産形成を組み合わせた対策は非常に効果的です。
開業医が実践すべき所得税対策
開業医は、事業所得の計算や経費の活用がポイントになります。
必要経費を適切に計上する
- 医療機器、消耗品、人件費、家賃、水道光熱費、通信費、学会費など
- 自宅兼クリニックの場合は按分処理を適切に行う
- 私的利用が混在する費用は注意(家族旅行、個人利用の自動車など)
小規模企業共済やiDeCoを活用する
- 小規模企業共済は掛金全額が所得控除対象+将来の退職金対策
- iDeCoも老後資金準備と節税を両立できる
医療法人化の検討
- 売上や利益が増えてきたら、法人化によって所得分散や法人税率の適用を検討する
法人化により役員報酬として給与所得に変えることで、給与所得控除や所得分散による節税も可能になります。
注意点|節税と脱税は紙一重
- 明らかに私的な支出を経費化するのはNG(税務調査で否認リスク)
- 制度を正しく理解し、適法な方法で節税を行うことが大切
- 制度改正にも注意し、最新情報をチェックする
特に開業医の場合、税務調査の対象になりやすいため、日頃から帳簿や証憑の管理を徹底しましょう。
まとめ|正しい知識と専門家のサポートを活用しよう
勤務医・開業医を問わず、所得税対策は「適切な知識」と「正しい手続き」が不可欠です。
特に開業医の方は、経費計上や法人化、退職金対策など、判断に迷う場面も多いため、税理士など専門家のサポートを活用することをおすすめします。
税理士ドットコムなどで専門家を探すのも一つの方法ですし、筆者が在籍する会計事務所でも医師の皆さまの状況に合わせた税務・財務のサポートを行っています。
どうぞお気軽にご相談ください。
次回予告|税理士に聞くべき3つのこと|医師の賢い税務対策とは
次回はシリーズ最終回として、「税理士に相談する際のポイント|何を聞くべきか、どこまで任せられるのか」をお届けします。
税理士に相談する際の「何を聞くべきか」「どこまで任せられるのか」といった実務的なポイントを、わかりやすくまとめてご紹介します。
「相談してみたいけれど、どこまでお願いできるの?」と感じている医師の方は、ぜひご覧ください。
→ 「税理士に相談する際のポイント|何を聞くべきか、どこまで任せられるのか」はこちら : 近日公開予定